LBP①:認知と情報の種類

LBP理論は「精神の働き」に基づいて人々を理解します。
ネット上などの多くの性格診断テストは「振る舞い(behave)」に基づいて人々をタイピングします。
認知は「意思決定」と「振る舞い(behave)」に大きな影響を及ぼしますが、人の「振る舞い(behave)」は認知だけで決まるわけではありません。
「認知」とは情報を取得して処理する精神の働きです。
全世界と、全ての物事や人々への理解は、過去に取得して処理した情報と、新たに取得して処理した情報に基づいています。
参照元
https://www.alittlebitofpersonality.com/
精神が行う4つのこと
人は思考(think)するとき、人の精神は自然と4つのことを行います。
|
①データと詳細(Data & Detail) 状況情報を分析する ↓ 疑問を呈して結論を出す |
②原則と傾向(Principle & Trend) 世界全体に対する理解を編纂する ↓ 世界の普遍的な傾向を理解する |
|
③行動と結果(Action & Consequence) 行動の結果を注視する ↓ 意思決定し計画を立てる |
④観察と動機(Observation & Motivation) 個人全体を観察する ↓ 人に対する性質的判断を下し、可能性を探求する |
・ある特定の状況や状態
・事態
・物事が機能する方法である基本的ルール
・物事の基本となる真実
・道徳的な規則
・行動指針
・物事が変化、発展する一般的な方向性
・趨勢、動向
・人の行いの背後にある心の働き
誰もが4つすべてを行いますが、各タイプはそれぞれ異なる順序でそれらを実行します。
知覚 vs 判断
知覚
|
①データと詳細 状況情報を分析する ↓ 疑問を呈して結論を出す |
|
| ④観察と動機 個人全体を観察する ↓ 人に対する性質的判断を下し可能性を探求する |
認知プロセスのうち2つは「知覚」であり、「知覚」は「①データと詳細」「④観察と動機」の2つです。
「知覚」は、「行動の可能性」と「個人と状況がどのように相互作用するか」にフォーカスします。
知覚タイプ(Pタイプ)は、「判断」よりも先に2つの「知覚」を行います。
彼女らは(物事を)調査することと、(状況に対して)受動的に対応することを好みます。
判断
|
②原則と傾向 世界全体に対する理解を編纂する ↓ 世界の普遍的な傾向を理解する | |
|
③行動と結果 人々の行動の結果を注視する ↓ 意思決定し計画を立てる |
認知プロセスのうち2つは「判断」であり、「判断」は「②原則と傾向」「③行動と結果」の2つです。
「判断」は、「行動計画」と「世界と行動の結果がどのように相互作用するか」にフォーカスします。
判断タイプ(Jタイプ)は、「知覚」よりも先に2つの「判断」を行います。
彼女らは、計画することと、行動することを好みます。
MBTIでは「認知の対象である情報」と「心理機能(Ni,Feなど)」は明確に区別されておらず、「知覚」とは情報を収集する機能(Si,Se,Ni,Ne)と定義しています。
LBP理論では「認知の対象である情報」と「心理機能(Ni,Feなど)」を別々に考えており、「知覚」とは「①データと詳細」「④観察と動機」のセットであると定義しています。
4つの情報の種類
「4つの精神の働き」に対応する「4つの情報の種類」がります。
情報の種類は、二重の二分法で分けられており、認知の対象となる全ての情報は必ず4つのうちの何れかに当てはまります。
「■情報」vs「□行動」
| ■情報 |
①データと詳細 状況の詳細 |
②原則と傾向 世界の働き |
| □行動 |
③行動と結果 決定とその結果 |
④観察と動機 「選択肢」と「人に対する性質判断」 |
「■情報」=「①データと詳細」「②原則と傾向」
「■情報」は物事そのもの(物事のありよう)にフォーカスします。
内向的タイプ(Iタイプ)は認知の第1ステップで「■情報」にフォーカスします。
内向的タイプは最初に自身の心の中を見て、物事がどのようになっているのか(物事のありよう)を理解します。
「□行動」=「③行動と結果」「④観察と動機」
「□行動」は人が行うこと(what people do)を理解する事にフォーカスします。
外向的タイプ(Eタイプ)は認知の第1ステップで「□行動」にフォーカスします。
外向的タイプは最初に外部を見て、人々の行うこと(what people do)を理解します。
「特定(Specific)」vs「普遍(Universal)」
| 特定(具体) | 普遍(全体) |
|
①データと詳細 状況の詳細 |
②原則と傾向 世界の働き |
|
③行動と結果 決定とその結果 |
④観察と動機 「選択肢」と「人に対する性質判断」 |
・ある一つのことに関係していること
・ある特定の事柄に関係していること
・世界または特定の範囲内のすべての物事に当てはまること
・極めて多くの物事にあてはまること
・一般的なこと
特定(具体)
「特定」=「①データと詳細」「③行動と結果」
「特定」は、ズームイン的な視点によって、情報の「特定的な適用(ある物事に用いる方法)」を理解することにフォーカスします。
IPとEJは認知の第1ステップが「特定」です。(=特定タイプ)
普遍(全体)
「普遍」=「②原則と傾向」「③行動と結果」
「普遍」は、ズームアウト的な視点によって、情報の「普遍的なパターン(Universal Pattern)」を理解することにフォーカスします。
EPとIJは認知の第1ステップが「普遍」です。(=普遍タイプ)
まとめ
4種類の精神の働き
|
①データと詳細 状況情報を分析する ↓ 疑問を呈して結論を出す |
②原則と傾向 世界全体に対する理解を編纂する ↓ 世界の普遍的な傾向を理解する |
|
③行動と結果 行動の結果を注視する ↓ 意思決定し計画を立てる |
④観察と動機 個人全体を観察する ↓ 人に対する性質的判断を下し、可能性を探求する |
4つの情報の種類
| 特定(具体) | 普遍(全体) | |
| ■情報 |
①データと詳細 状況の詳細 |
②原則と傾向 世界の働き |
| □行動 |
③行動と結果 決定とその結果 |
④観察と動機 「選択肢」と「人に対する性質判断」 |
各タイプが最初に行うこと
EP:最初に、人々の動機を観察するために、普遍的な「④反応」を観察する
IP:最初に、結論を導くために、特定の「①データと詳細」を考える
IJ:最初に、傾向を理解するために、普遍的な「②原則」を考える
EJ:最初に、行動の結果を理解するために、特定の「③行動」を注視する
各タイプの認知ステップ
EP
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 知覚 | 判断 | ||
| 観察() | 詳細() | 原則() | 行動() |
| △Se/Ne | ▲Fi/Ti | △Fe/Te | ▲Si/Ni |
IP
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 知覚 | 判断 | ||
| 詳細() | 観察() | 行動() | 原則() |
| ▲Fi/Ti | △Se/Ne | ▲Si/Ni | △Fe/Te |
IJ
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 判断 | 知覚 | ||
| 原則() | 行動() | 詳細() | 観察() |
| ▲Si/Ni | △Fe/Te | ▲Fi/Ti | △Se/Ne |
EJ
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 判断 | 知覚 | ||
| 行動() | 原則() | 観察() | 詳細() |
| △Fe/Te | ▲Si/Ni | △Se/Ne | ▲Fi/Ti |




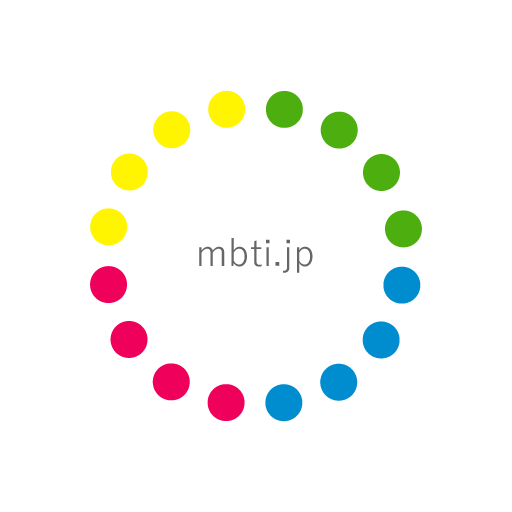
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません