世界観

人々が世界をどのように見るかは、認知と経験がどのように相互作用するかに基づきます。
認知パターンに基づいて、各タイプは同じ経験をまったく異なる方法で解釈します。
それらの経験を通じて、それぞれのタイプは異なる世界観に向かいます。
I、E、F、Tタイプ
Iタイプは自身の頭の中を主機能とし、理論上の人々(人々全般)にフォーカスします。
Eタイプは自身の外の世界を取り込むことを主機能とし、実在の人々(特定の人々)にフォーカスします。
Fタイプは人や物の意義を重視し、人に対して楽観的(Optimistic)な傾向を持ちます。
Tタイプは人や物の有用性を重視し、人に対して悲観的(Pessimistic)な傾向を持ちます。
IFタイプ
理想主義的(Idealistic)
人々全体はGood(善、良い)で、有意義であると考える傾向を持つ。
冷笑的になるとき、それは実在の人々の欠点についてである傾向がある。
EFタイプ
楽観的(Optimistic)
実在の人々はGood(善、良い)で、有意義であると考える傾向を持つ。
冷笑的になるとき、それは人々全般の欠点についてである傾向がある。
ITタイプ
悲観的(Pessimistic)
人々全般はBad(悪、良くない)で、有用性がないと考える傾向がある。
楽観的になるとき、それは自身にとって重要な個人(特定の人々)についてである傾向がある。
ETタイプ
懐疑的(Skeptical)
実在の人々はBad(悪、良くない)で、有用性がないと考える傾向がある。
楽観的になるとき、それは自身にとって重要な人々全般(理論上の人々)についてである傾向がある。
S、N、J、Pタイプ
Sタイプは直線的(liner)・文字通り(literal)・現実的(on the ground)な方法で世界をとらえ、現状維持や既存のものを守ることに関心を持ちます。
Nタイプは概念的(conceptual)、非線形(non-linear)、広範な方法(ar-reaching)で世界をとらえ、物事を変えてその可能性を最大限に引き出すことに関心を持ちます。
Jタイプは「③行動と結果」と「②物事が機能する方法に関する原則」の関係性にフォーカスし、世界や集団が向かう方向性を専門とします。
Pタイプは「①データと物事のありよう」と「④個人の動機(心)」の関係性にフォーカスし、世界と人を探求することを専門とします。
NJ
変革者(ゲームチェンジャー)
世界を変えることにフォーカスする。
NP
モチベーター(他者を鼓舞し、動機を誘因する人)
自分自身や個人を変えることにフォーカスする。
SJ
世界の保護者
世界を保護する(同じに保つ)ことにフォーカスする。
SP
個人主義者(自他の個性の擁護者)
自分自身や個人を保護する(同じに保つ)ことにフォーカスする。
16タイプの世界観
INFJ
理想主義的な変革者
人々全般はGood(善、良い)だと思う傾向があり、世界の悪い部分を変えることが可能だと信じる。
INFP
理想主義的なモチベーター
人々全般がGood(善、良い)だと思う傾向があり、自分や個人の悪い部分を変えることが可能だと信じる。
ISFJ
理想主義的な世界の保護者
人々全般がGood(善、良い)だと思う傾向があり、自身が愛する世界の各部分を保護したいと願う。
ISFP
理想主義的な個人主義者
人々全般がGood(善、良い)だと思う傾向があり、自身が愛する人々をありのままに保ちたいと願う。
ENFJ
楽観的な変革者
実在の人々はGood(善、良い)だと思う傾向があり、世界の悪い部分を変えることが可能だと信じる。
ENFP
楽観的なモチベーター
実在の人々はGood(善、良い)だと思う傾向があり、自身や個人の悪い部分を変えることが可能だと信じる。
ESFJ
楽観的な世界の保護者
実在の人々はGood(善、良い)だと思う傾向があり、自身の愛する世界の各部分を保護したいと願う。
ESFP
楽観的な個人主義者
実在の人々はGood(善、良い)だと思う傾向があり、自身が愛する人々のありのままに保ちたいと願う。
INTJ
悲観的な変革者
人々全般はBad(悪、良くない)だと思う傾向があり、世界の悪い部分を変えようとする。
INTP
悲観的なモチベーター
人々全般はBad(悪、良くない)だと思う傾向があり、自身や個人の悪い部分を変えようとする。
ISTJ
悲観的な世界の保護者
人々全般はBad(悪、良くない)だと思う傾向があり、自身が愛する世界の各部分を保護しようとする。
ISTP
悲観的な個人主義者
人々全般はBad(悪、良くない)だと思う傾向があり、自身が愛する人々のありのままを保とうとする。
ENTJ
懐疑的な変革者
実在の人々はBad(悪、良くない)だと思う傾向があり、世界の悪い部分を変えようとする。
ENTP
懐疑的なモチベーター
実在の人々はBad(悪、良くない)だと思う傾向があり、自身や個人の悪い部分を変えようとする。
ESTJ
懐疑的な世界の保護者
実在の人はBad(悪、良くない)だと思う傾向があり、自身が愛する世界の各部分を保護しようとする。
ESTP
懐疑的な個人主義者
実在の人々はBad(悪、良くない)だと思う傾向があり、自身が愛する人々のありのままを保とうとする。
最後に
これらはいずれも健全で必要な世界観です
人が物事を善か悪かに単純化しすぎるとき、人は判断ミスを犯すものです。
すべてがうまくいっていると信じたり、あるいは救うべきものが全くないと信じたりすると、一時的にせよ、視野が狭まり、不健康になるのです。
人間であれば、自分が得意とする分野や独特な長所が危うくなることを恐れると、そうなってしまうのです。
IJは世界のあるべき姿を守ろうと必死になり、EJは自身のグループが無に帰すことを恐れ、IPは自分の専門分野が無意味であると感じ、EPが自分という存在が重要でないことを恐れます。
自分の人生や、世界において重要視していたものが失われるという危険を感じるとき、正気を保とうとして肯定か否定かの極端な判断にしがみつくのです。



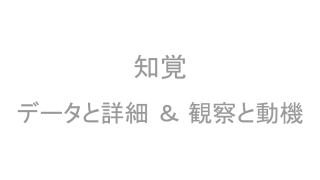
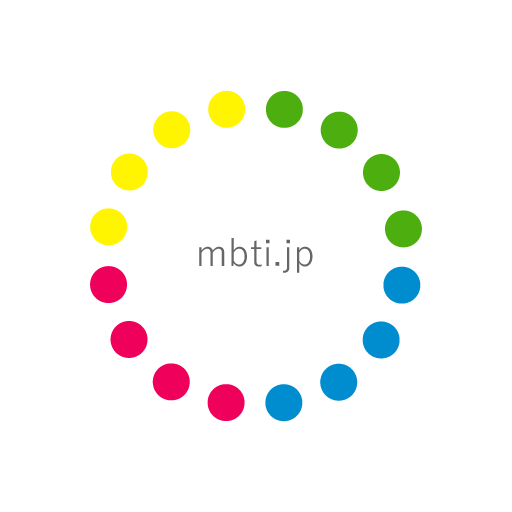
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません